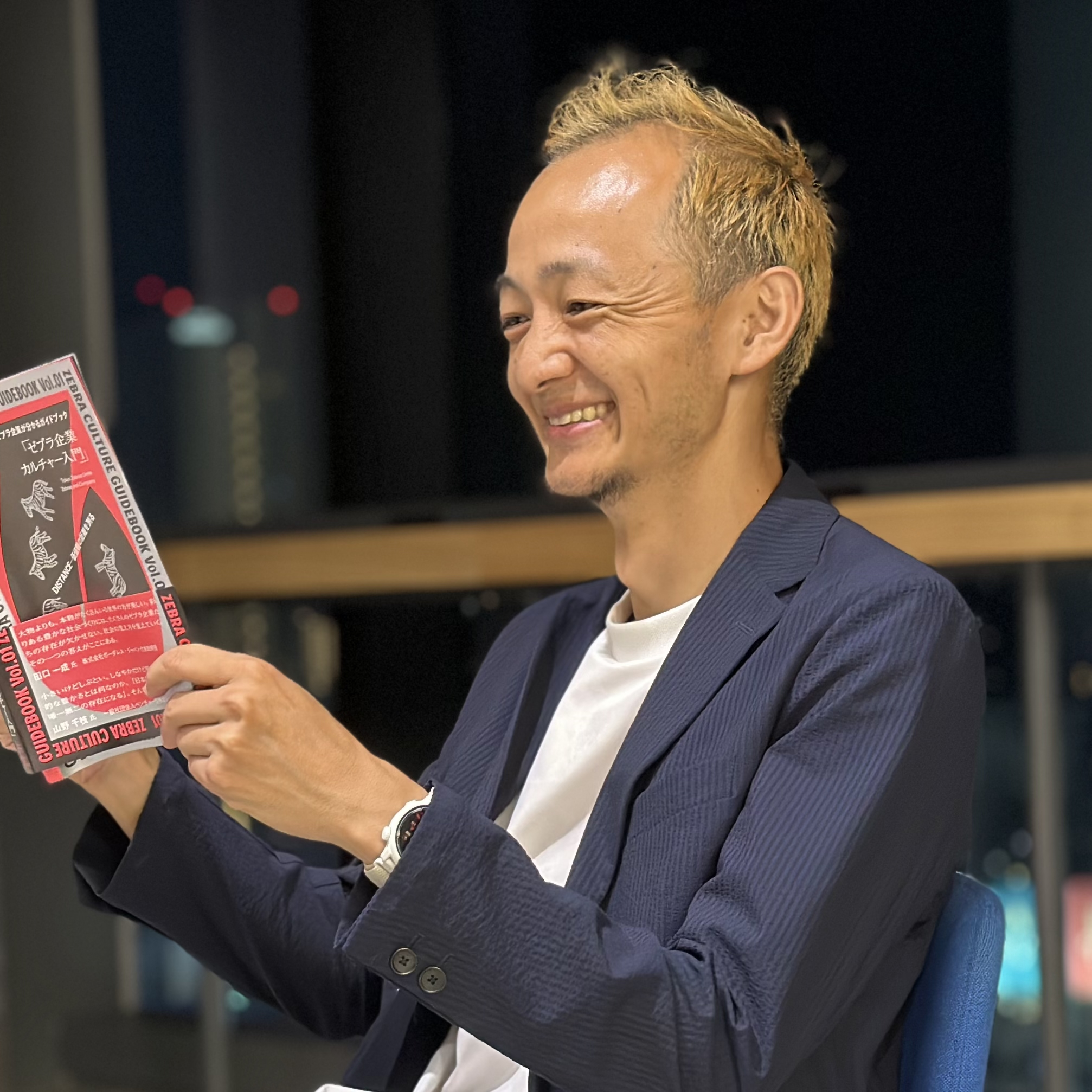“言い訳しない力”世界陸上のアスリートにみるメンタルトレーニング
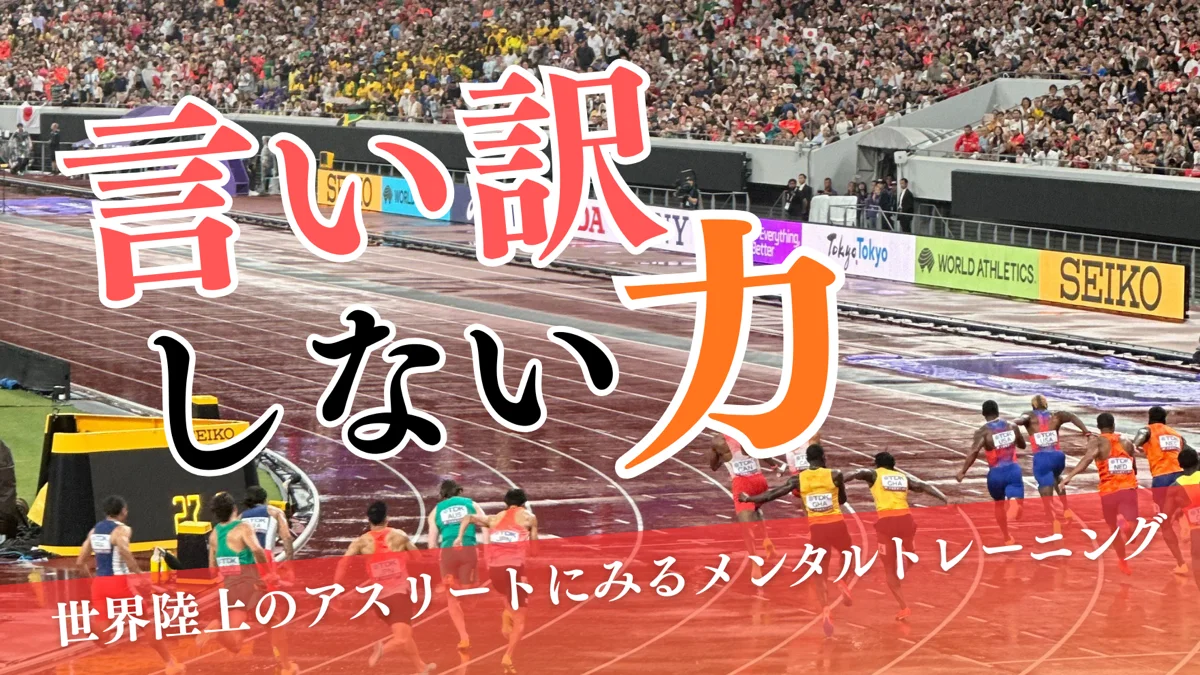
世界陸上、テレビで観ていますか?自国開催ということもあって、会場に足を運んだ方もいらっしゃいますでしょうか?新国立競技場満員の盛り上がり、観客の声援、その熱量が選手たちに確実に伝わっているのを感じます。
私自身、学生時代は、筑波大学体育専門学群でスポーツ科学を学び、学生時代は箱根駅伝出場を目指して青春のすべてを競技に注いできました。しかし、夢は叶わず、陸上競技の世界とは完全に距離をとりました。
しかし、人材教育コンサルティングの世界に飛び込み、心理学や脳科学を学ぶにつれて、「なぜ現役時代に結果を出せなかったのか」を痛感しました。あのとき知っていれば・・・その思いが、原動力となり、現役アスリートのメンタルトレーニングや引退後のセカンドキャリア、デュアルキャリアの相談に関わることをライフワークにしてきました。
世界陸上の優れたパフォーマンスが生み出される瞬間の感動はもちろんですが、それ以上に、「思い通りにいかないときに、選手たちがどう振る舞うか」に心を揺さぶられることが多いです。今回は、そんなアスリートの側面に触れてみたいと思います。
不運・理不尽とどう向き合うか――三浦選手のケース
男子 3000m 障害決勝。三浦龍司選手は、最後の直線で他選手との接触に巻き込まれ、体勢を崩し、一気に失速してしまいました。結果は8位。メダルには届きませんでした。
けれど、興味深いのは、その後の彼の発言です。
「運はつきもの」
この一言には、無念さを含みながらも、それをただの “言い訳” にしない態度がにじみ出て いるように感じました。さらに
レース内でできることは全部出し尽くした
典型的な最後のサバイバルレースだったけど、しっかりと落ち着いて行くことができたし、四年前に東京五輪で走った時より確実に成長できている。
という自己の評価を含めた言葉もありました。
これらの発言から読み取れるのは、
- 自分がコントロールできない出来事(運・接触など)を、不当な責めに変えないこと。
- できたことに目を向ける自己評価の力。
- 成長マインド:結果が期待通りでなくても、自分の進化を感じ取る視点を持っている。
ここに見えるのは、心理学でいうコントロール可能領域への集中(自分が影響できること=準備・判断・走り方)と、再評価(リフレーミング)のスキルです。起きた事実は変えられない。変えられるのはいま・ここの自分の在り方。その原則を、最高峰の緊張下で実装している。それがトップの“平常心”の正体です。
と言葉で書いてしまうと簡単そうに見える「メンタルコントロール」の基本ですが、とてつもないプレッシャーがかかり、日常とは全く異なる環境でそれを実践することは、決して簡単なものではありません。
スタートの一瞬、準備の時間――泉谷選手のケース
同じく注目されたのが、泉谷駿介選手(110m ハードル)のケースです。前回大会で入賞しており、メダルも期待された選手ですが、スタートで出遅れて、予選落ちをしてしまいます。
スタートでやられましたね。横の選手がピクついてしまったので、それに惑わされてしまいました
と、外的要因を説明しつつも自分の反応として言語化しています。ここでも“自分のコントロール”に話を引き寄せている点がポイントと言えます。
さらに、その後、まさかの「繰り上げで準決勝進出」となりますが、それを知らされたのは、準決勝の1時間前で、自宅で見ていた時だったとのこと。実際にウォーミングアップは15~20分程度しかできなかったといいます。
「このような結果になってしまって申し訳ない…またがんばれるように精神面を整えていきたい」
「ネタにして、強く生きていくしかない」
泉谷選手の振る舞いには、次のようなメンタルトレーニングの要素があると言えます。
- 一瞬での切り替え:予選での不本意なスタートを悔しがるだけで終わらせず、「今回の反省点を見て直したい」と前を向く。
- 準備不足・予期せぬ状況への対応:準決勝という舞台を知ったのが本番直前という、理想とはいえない状況でも、「話のネタにして強く生きていくしかない」とユーモアを交えながら受け止める態度。ユーモアは、レジリエンス(心理的回復力)を構成する重要な要素です。
2人に共通しているのは、不運や他者の行為を糾弾するのではなく、自分に返ってくる意味を言葉にする姿勢と言えます。
3. トップの「言い訳しない」は、何が違うのか(心理スキル分解)
試合直後に冷静に語る二人から、以下の5つのスキルが見えます。
- ラベリング(感情を名指す)
「悔しい」「驚いた」など、湧き上がる感情にラベルを貼る。感情は事実ではなく内的反応であると区別する。
→ 感情に飲まれず、行動のハンドルを握り直せる。 - コントロール焦点
「自分が変えられることは何か?」を即座に仕分ける(準備・集中・手順・対応)。
→ 他者や運、不運に意識を持っていかれない。 - 再評価(リフレーミング)
同じ出来事を学習機会に言い換える。「面白さも、難しさも」等。
→ 自己効力感を維持し、次アクションを決められる。 - ミクロ目標
「次の障害一本」「最初の3ハードル」など、いまと次にフォーカスする短距離目標。
→ プレッシャー下での遂行を安定化。 - セルフコンパッション+ユーモア
自責に偏らず、事実と改善点を分解。「ネタにして強く生きる」等。
→ 緊張・失敗経験を“生かす材料”に変換。
これらは、アスリートが磨き持っているものではあると言えますが、若い時から最初から持っていたわけではないでしょう。身体と同様に、メンタルも鍛えてきたと言えるでしょう。つまり、メンタルは才能ではなく、技術と習慣と言えます。
5. 仕事やプライベートに効く「メンタル・ドリル」
これらのメンタルトレーニングを、日常バージョンにしてみました。会議前、商談前、面接前などにどうぞ。
STEP1|落ち着く(5秒)
感情に振り回されず、まず深呼吸して、落ち着きます。
STEP2|事実の棚卸し(30秒)
「起きたこと」を短文で整理する。
(例:予定が前倒しになった/相手が遅れた/会議室が取れない)。
STEP3|コントロール仕分け(30秒)
○=自分で変えられる
×=変えられない。
例:話し方・構成・時間配分=○/相手の機嫌=×。
STEP4|言い換え(30秒)
ネガティブ思考をリフレーム(違う言葉に置き換える)
(例:「時間がない」→「核心だけを話せる」)
この4ステップは、感情の波を認めつつ、行動の主導権を取り戻すためのルートです。最初は、メンタルコーチに手伝ってもらったり、書き出してみたりが効果的ですが、日頃から、実践することで、自然と“切り替わりやすい脳”になります。
6. 「聴いてもらう」は最速の整え方──LivelyTalkという選択肢
ここまで読んで、「分かるけど、一人では続かない」と感じた方へ。
話す=外に出すことは、自己認知を深めるのに非常に効果的です。頭の中のもつれは、声にすると整理されます。
LivelyTalkは、メンタルコーチではないですが、あなたの中にある感情を一緒に吐き出すお手伝いをする場所です。そして、ホストは、あなたの言葉を受け止める“聴くプロ”です。モヤモヤや悔しさ、不安を、安全に言語化して、
- 何が事実で、
- 何が自分の解釈で、
- どこが変えられるか(○)、どこは変えられないか(×)、
を一緒に仕分ける。
そのうえで「次の一歩」をあなた自身が決められるように整えます。
「いま抱えていることを、LivelyTalkで5分だけ話す」
それで十分、動き出すきっかけになると思います。
ぜひ、一度、LivelyTalkで自分の内面と向き合う一歩をしてみてください。
きっとあなたの“言い訳しない強さ”は、今日から育てられるはずです。